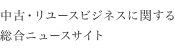ものばんく×下関市立大学、「質屋」を共同研究
2025年08月19日
質店とオークションを運営するmonobank(山口県下関市)と公立大学法人下関市立大学(山口県下関市)は、「質屋の経済学」をテーマに共同研究を開始する。約800年の歴史を持つ日本の伝統的な金融ビジネスである「質屋」を学術的に体系化。現代社会における経済的・社会的意義を再定義することを目指す。
研究期間は3年間で、総予算は750万円。講座ではまず、質屋約800年の歴史を分析する。次に、学生たちはものばんくの店舗などでフィールドワークを行い、現代リユース市場での質店の実態を調査する。カリキュラムは経済学の枠にとどまらず、歴史的な経営戦略やサステナビリティの文脈、哲学的な視点も導入。こうした人文科学的なアプローチを融合させ、社会における質店の普遍的な価値と未来の可能性を深く探求していく。講義は経済学部だけでなく全学部を対象とし、座学と実践を組み合わせた教育を提供する。
 monobank 吉田悟社長と下関市立大学学長 韓昌完氏
monobank 吉田悟社長と下関市立大学学長 韓昌完氏
今回の共同研究には、吉田悟社長の経営戦略としての狙いも含まれる。24歳で家業を継いだ際、若者向けにマーケティングを転換した経験を活かし、現在の50代中心の顧客層から次の20〜30代にアプローチするため、学生の視点を取り入れる。また、この講座を従来の採用広告に代わるリクルーティング活動と位置づけ、業界の魅力を伝え、将来を担う人材の採用につなげる意図もある。
吉田社長は「質店は昭和20年代のピーク時約2万軒から約1500軒に激減し、一方でリユース専門店は約2万軒規模に拡大した。かつて質店は、質草を担保に貸付けをすることで、地域社会のセーフティネットとして機能していた。しかし今は買取が主流となり、その役割が失われつつある」と指摘。
「資本主義的な競争とは一線を画し、セーフティネットとしての役割を再確立したい」と今後の展望を語る。今回の研究を通じて、質店の社会的意義を理論的に裏付け、次世代への指南書となるような成果を目指す。
第614号(2025/08/25発行)4面